この記事では、証券トレーダーに関して、就活生からよくある質問をQ&A形式でまとめました。
筆者の8年間の実体験をもとにしたリアルな回答です。
この記事を読むと
📌証券トレーダーの仕事をより深く理解できる
📌証券トレーダーを目指す就活生にとって重要な情報を得られる
📌証券トレーダーの実態が分かる

かなりの分量なので、↓の目次から知りたい質問に飛ぶことをおすすめします。
Contents
- 1 証券トレーダーについての記事
- 2 【証券トレーダーの仕事内容・働き方】について
- 2.1 Q. トレーダーは1日中画面に張り付いてトレードしているのですか?
- 2.2 Q. AIやアルゴリズム、HFTが進化しても、人間のトレーダーは必要ですか?
- 2.3 Q. 在宅勤務やリモートワークは可能ですか?
- 2.4 Q. トレード以外にはどんな業務がありますか?
- 2.5 Q. どのようなトレーディングツールを使っていますか?
- 2.6 Q. トレードのマニュアルなどはあるのでしょうか?
- 2.7 Q. どのような手法で取引していますか?
- 2.8 Q. どれくらいの金額を動かしていますか?
- 2.9 Q. 何年くらい働けば一人前とみなされますか?
- 2.10 Q. 一人で何銘柄くらい担当していますか?
- 2.11 Q. ディーラー?トレーダー?どう違うのですか?
- 3 【証券トレーダーの収入・ボーナス・待遇】について
- 4 【証券トレーダーのキャリアパス・将来性】について
- 5 就活生向け【証券トレーダーへの就職】について
- 6 【証券トレーダーの精神面・人間関係】について
- 7 【その他の質問、金融業界、株式市場全般】について
- 8 まとめ
証券トレーダーについての記事
証券会社ごとのトレーダーの違いや収入、マーケットメイク業務の詳細などについては別の記事で詳しく説明しています。
直接この記事に来てしまった方はぜひお読みください。
-

-
証券トレーダーの仕事とは?大手証券トレーダー経験者が仕事内容・役割を徹底解説
2025/7/16
「トレーダー」と聞くと、どんなイメージを持つでしょうか? チャートとにらめっこしながら日々トレードを繰り返す──そんな姿を思い浮かべる方も多いかもしれません。 でも実は、「トレーダー」と名のつく仕事に ...
-

-
マーケットメイクとは?証券トレーダーが担う役割と仕組みを解説
2025/7/18
「証券会社のトレーダーって、どんな仕事をしているの?」 「マーケットメイクって聞いたことあるけど、具体的に何をするの?」 そんな疑問を持つ方に向けて、この記事では証券会社のトレーダーが担う『マーケット ...
-

-
証券トレーダーの収入の仕組みと年収レンジ【実体験をもとに紹介】
2025/7/19
「大手の証券トレーダーって、実際どのくらい稼げるの?」 金融業界やトレーダー職に興味を持っている人にとって、年収や報酬体系はやはり気になるポイントではないでしょうか。 結論から先にいうと、だいたい下記 ...
【証券トレーダーの仕事内容・働き方】について

Q. トレーダーは1日中画面に張り付いてトレードしているのですか?
A. 基本的にはデスクに座って画面を見ていますが、離席できないわけではありません。
おそらくこの質問は個人トレーダーの延長のようなイメージで考えているように思えます。
もちろん、瞬間的に大きなポジションをとったために張り付いていなければまずい状況もありますが、一瞬も離席できないほどのリスクをとるのは証券トレーダーとしてはやりすぎです。
どちらかといえば、ポジションがどうのではなく、顧客からのリクエストがいつ来るか分からないために、常にデスクにいるというのが正しいです。
トイレや食事などで席を外していた場合は、他のトレーダーが対応したり、社用携帯で「すぐ戻るから待ってくれ」、と伝えることで納得してもらえることが多いです。(そうでない場合もあります。)
Q. AIやアルゴリズム、HFTが進化しても、人間のトレーダーは必要ですか?
A. 必要と言い切ってしまってよいと思います。
テクノロジーの発達でトレーダーの仕事が奪われるとよく耳にしますが、筆者はあまりそうは思いません。
確かに、注文の執行分野におけるAIやアルゴリズムの発達は凄まじく、HFTの執行速度に人間が追いつけるはずはありません。
このために、単純に取引所に上から指示された注文を流すだけの「トレーダー」の仕事は減っていくと考えられます。
一方で、証券トレーダーは自己勘定で利益を得るためのトレードをおこなっており、AI、アルゴリズム、HFTと競合しているというより、むしろテクノロジーを利用する立場にあります。

そもそもお金を稼ぎたいと思っているのは人間なので、マーケット参加者が全員AIになったとしても、そのAIを動かしている人間の欲望と恐怖が相場の歪み(=トレーダーの収益の源泉)を生み出すことは間違いないと筆者は思います。
また、大口のマーケットメイクは麻雀やポーカーのように、非常に複雑で不確定な要素が多い高度に裁量的な仕事です。
もしこの仕事が完全に機械に置き換わってしまうのであれば、そのような時代には、他の多くの職種も消滅しまうのではないでしょうか。
HFTとは
高速取引の黎明期をのぞき見る
Q. 在宅勤務やリモートワークは可能ですか?
A. 可能ですが、一定以上の出社が義務付けられている会社も多いです。
情報管理上の懸念から、金融機関の社員が在宅やリモートで仕事をすることに危険が伴うのは確かです。
しかし、職務の遂行に支障があるかどうかという視点で言えば、ほとんど問題ないと筆者は考えます。
実際、2020年以降ではトレーディングフロアのほとんどがフル在宅に近い状態で働いていましたが、通常営業が継続できていました。
ツール、モニターなどの作業環境やコミュニケーションの取りやすさという観点ではもちろん出社した方が仕事はスムーズです。
その後も柔軟な働き方を取り入れるという名目で、希望者は在宅も可というところが多いですが、「トレーダーは原則出社」という会社もあります。

「柔軟な働き方」という世間体のいいワードを公に標榜しながら、こうして頑なに出社を要求する矛盾した会社の姿勢に筆者は納得できず、退職理由の一つとなりました。
Q. トレード以外にはどんな業務がありますか?
A. ブッキング(トレードの帳簿付け)、損益の報告、ミーティング、採用活動などがあります。
デリバティブなど契約内容が複雑な商品を担当する場合は、正しくツールに詳細を入力(ブッキング)するだけでも時間がかかる場合があります。
損益の報告は全トレーダーの義務です。
ブッキングが完了次第、マネージャーに一日の損益と残ったリスクを報告します。
ミーティングでは、顧客動向とマーケット情報などをセールスと共有する定例ミーティングの他、商品開発部署と新商品について話し合ったり、ビジネス全体の方向性を議論するものまであります。
採用活動も部署単位で行われることが一般的で、各部署に窓口となる担当者がおり、人事と協力してインターンから個別面談までの対応を行います。

筆者はトレーダーの傍ら、長らくこの採用担当をやっていました。
Q. どのようなトレーディングツールを使っていますか?
A. 情報源はBloombergアカウントです。リスク管理やトレードツールは自社開発が多いですが、外部開発ツールを法人購入している場合があります。
損益やポジションをモニターするためのリスク管理ツールは、各社で独自の統合型システムを開発しており、管理用のITチームが配備されていることが多いです。
ニュースやマーケット監視用のツールは、セールス、トレーダー、顧客のほとんどがBloomberg社のアカウントを保有しており、どの会社でも全員が同じものを使用しています。
Bloombergアカウントを持つことによって、社外ともチャットで連絡できるという点がポイントです。
法人契約は一人あたり月額(!)30万円ほどらしく、個人では元を取るのが難しいです。
ちなみに画面の様子は楽天証券のマーケットスピード1に似ています。
トレードツールは会社によって大きくばらつきがあり、自社開発のところと、外部ベンダーのツールを使っているところがあります。
業界の規制や、誤発注対策などにより、何段階も確認画面が出てきたりするため、実はあまり使い勝手がいいと言えないものが多いです。

筆者の感覚では、松井証券のネットストック・ハイスピードの方が数段使いやすいと思っています。
ただし板乗りスピードという点では証券トレーダーの圧勝で、即座に板に反映されます。
Q. トレードのマニュアルなどはあるのでしょうか?
A. プライシングやブッキング作業などはマニュアル化されている場合があります。トレードそのものに対するマニュアルはありません。
つまり、仕事上必要な作業についてはマニュアルが存在しえますが、「いつ、何を、どのように売買するか」というものは、基本的に存在しないということです。
したがって、証券トレーダーにはマニュアルがあって、それに従えばお金を稼げるようになる、という認識は誤りです。
自分自身にとっての正解を各自で探るしかありません。
Q. どのような手法で取引していますか?
A. 人によってさまざまで、必ずこれというものはありません。
こちらもおそらく個人トレーダーの延長のイメージから来る質問だと思います。
手法以前の問題として、証券トレーダーはポジションを「とらされる側」なので、常に好きなタイミングで取引ができるわけではありません。
スタート地点から個人トレーダーとは異なり、
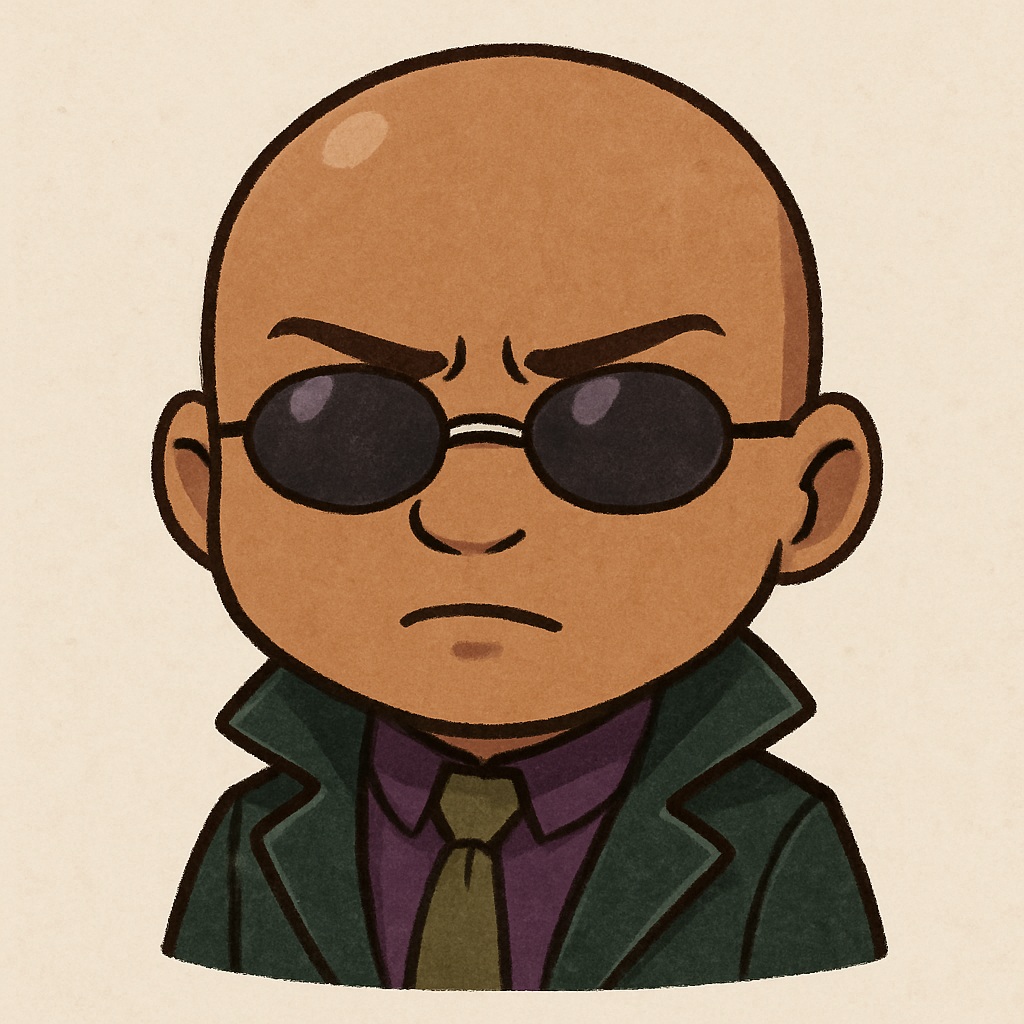
引き受けたポジションをこれからどうしよう
というところから始まります。
また、担当商品によっても特徴が全く変わってくるため、例えばオプショントレーダーと現物株トレーダーでは、マーケットの見方から違ってきます。
したがって、やはり証券トレーダーの手法は人によって異なり、各自が自分に合うようなやり方をしている、という無難な回答になってしまいます。
Q. どれくらいの金額を動かしていますか?
A. 会社のリスクリミットと担当商品の流動性によって異なります。
意外かもしれませんが、この質問に正しく答えるのは難しいです。
個人トレーダーやヘッジファンドマネージャーの場合は簡単で、自己資金の金額がそのまま運用金額となります。
プロップファームの証券ディーラーも同様に、この金額までなら扱ってOK、と決まっていることでしょう。
プロップファームのディーラーが分かる書籍
アメリカのプロップファーム
しかし、大手証券トレーダーの仕事は資金運用ではありません。
顧客のニーズに応えるために、必要があれば外部から資金を調達してトレードを成立させます。
したがって、証券トレーダーの取り扱い金額は、会社がどこまでリスクをとれるか、と担当商品の流動性によって自然と決まってくる形になります。
商品と流動性の例
日本の個別株オプション:10億円でもかなり大きなトレード
日経平均先物ラージ:500枚(=約150億円規模)でも処分できる
単純な肌感覚だけを伝えるならば、日本の株トレーダーにとって大型株で1,000万円のポジションは小さめ、10億円はけっこう大きい、といったイメージでしょうか。
Q. 何年くらい働けば一人前とみなされますか?
A. 3年目くらいから転職するトレーダーが急増します。
実際は担当商品によって覚えるべき項目の量が違うため一概にはいえず、デリバティブ担当だと一通りマスターするために3~5年くらい必要かもしれません。
3年目くらいから転職組が発生するのは、おそらく外資系の採用戦略によるものだと思います。
特に日系証券では社内の研修制度が充実しているところも多いため、2~3年経験した若手を狙ってヘッドハンティングするという戦略が横行しています。
Q. 一人で何銘柄くらい担当していますか?
A. 銘柄ごとではなく、商品や地域によって分かれていることが多いです。
よく聞かれる質問ですが、この銘柄、このセクターだけ担当、ということはあまりないです。
日本の現物株担当であれば日本株すべて、アジアのインデックスオプション担当であれば日経、ハンセン、NIFTY、KOSDAQなど一通り見る、という具合です。
外資系のトレーダーは一人でカバーする範囲がより広い傾向があります。
一方で、銘柄ごとで流動性に差があることが多く、頻繁にトレードされるものとそうでないものがあるため、実際には担当商品の全銘柄を見ているのではなく、その中で数銘柄を重点監視しているというのがリアルです。
Q. ディーラー?トレーダー?どう違うのですか?
A. 投資銀行や証券会社のトレーダーを「ディーラー」と呼びます。
一般的に「セルサイド」と呼ばれている業者に所属するトレーダーを「ディーラー」と呼びます。
セルサイドとは、手数料を受け取る立場にある「業者」のことです。
証券会社の中にはマーケットメイクなど顧客対応を一切行わず、自己勘定取引のみで会社の資金を運用しているところ(プロップファーム)があります。
こちらは手数料を受け取るビジネスをやっているわけではないですが、これも「ディーリング業務」、トレーダーは「ディーラー」と呼ばれます。
一方で、ヘッジファンドに所属して大きな顧客資金を運用している人は「ディーラー」とは呼ばれません。
"証券トレーダー = ディーラー"と簡単に理解してもよいと思います。
"工藤哲哉(著)百戦錬磨のディーリング部長が伝授する「株式ディーラー」プロの実践教本"という書籍で、運用ディーラーの仕事について解説されています。
プロップファームのディーラーが分かる書籍
こちらはアメリカのプロップファームとその戦略を紹介した書籍です。
アメリカのプロップファーム
【証券トレーダーの収入・ボーナス・待遇】について

Q. ボーナスはどうやって決まるのですか?
A. 本人の損益が最も重要ですが、基準が曖昧なことも多いです。
どの会社でも、トレーダーのボーナスは「稼いだ金額」がその大部分を占めているというのは間違いありません。
会社によっては歩合制のところもあるようですが、多くのパターンとしては、
ボーナス = 本人の稼ぎ × 肩書 × 会社の業績 × ビジネスへの貢献度
という構図になっていると考えられます。
特に「ビジネスに対する貢献度」は定性的な要素が強く、いかに自己アピールが上手か、という社内政治的なニュアンスが多く含まれています。
Q. 新人トレーダーでもすぐに大金を稼げるのですか?
A. 1~2年目の証券トレーダーが管理職並のボーナスを得ることは稀です。
新人でもマーケットで大きく稼げばそれなりの給料を期待できますが、肩書によって上限幅が設けられていることが多いようで、単純な歩合システムとは異なります。
新人時代にそれなりに稼ぎ、同じ上司についたまま昇進できた場合は、過去の業績を評価してくれることがあり、5~6年目ぐらいから急激に報酬が増える、というパターンもあるようです。
Q. 損失を出すとすぐにクビになったり給料が下がったりしますか?
A. 外資系ではかなりあり得ます。日系は少しゆるいようです。
稼ぐことが期待されている仕事なので、年間でマイナスを出した場合のトレーダーに対する評価は非常に厳しくなります。
外資系では、自分の部下が損失を出したことを追求されたマネージャーが、
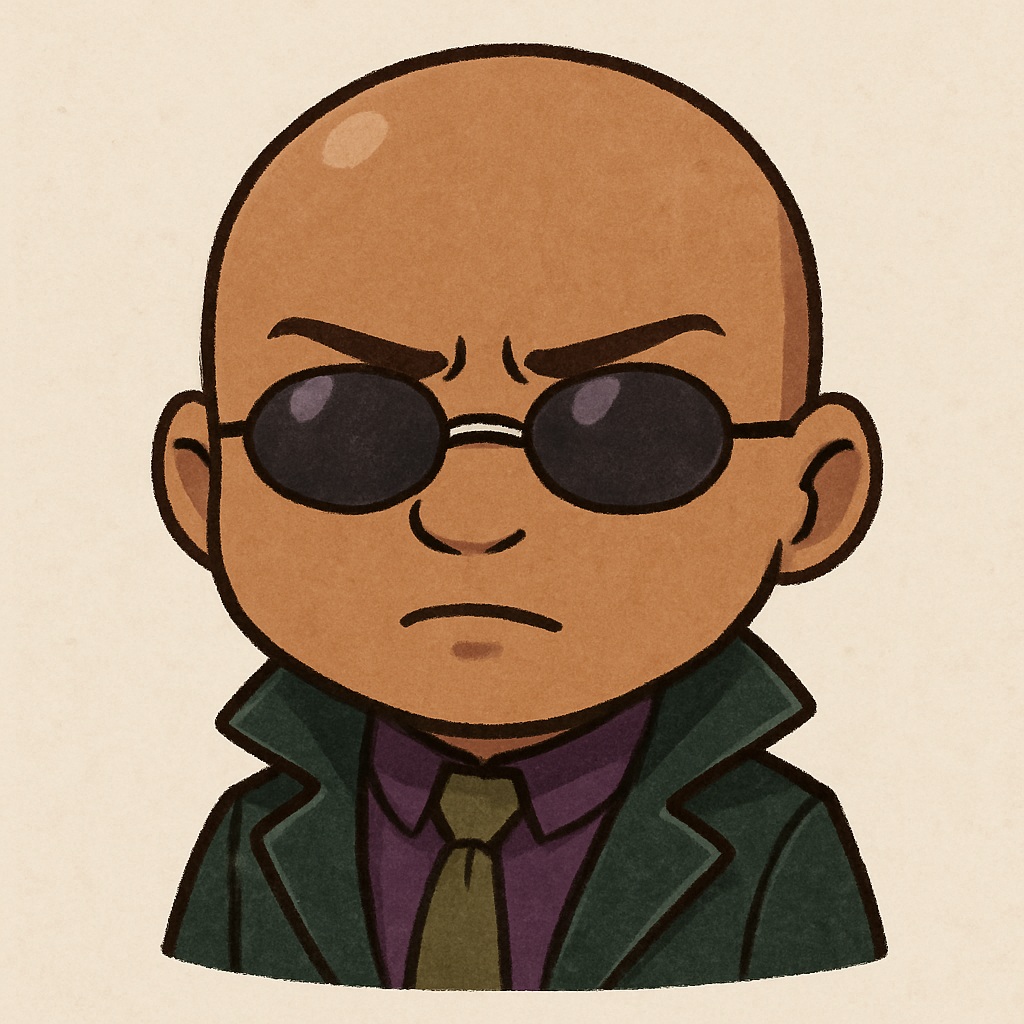
とりあえず部下をクビにしてなんとかしようとしている感を出しておこう
と、現担当者を別の人物に入れ替えるといった理不尽なパターンもよくあります。
一方で、一旦クビになったとしても、トレーダーになれるポテンシャルを持った人材は貴重なので、すぐに競合他社で働き始めることも非常に多いです。
ポストに空きがあれば、転職活動が絶望的に難しいということはありません。前より給料は下がるかもしれませんが。
また、トレーダーの給料は年功序列的要素もゼロではないですが、ボーナスの変動幅があまりにも大きいため、自分自身と会社の業績によって大きくスイングするのが普通です。
年度の成績がマイナスだったり、会社が大赤字であれば、「ないものは払えない」という当然のことが起きているだけなので受け入れるしかありません。
Q. 外資系と日系で収入の違いはどれくらいありますか?
A. 入社年数が浅いうちは外資が1.5~3倍くらい、ベテランになってくるとまちまちです。
こちらは別の記事で記載したリストで、非常におおまかながら、年収の参考値を肩書別に表現しています。あくまで参考値です。
| アナリスト(AN) 新人 | アソシエイト(AS) 係長クラス | ヴァイスプレジデント(VP) 課長クラス | エグゼクティブ・ディレクター(ED) 課長クラス | マネージング・ディレクター(MD) 部長クラス |
| 500万円~900万円 | 800万円~1,500万円 | 1,000万円~3,000万円 | 2,000万円~5,000万円 | 3,000万円~1億円(数億円に達することも) |
少人数で業務を回しているために基本的には外資が高く、この表の上限付近やそれ以上になることが多いと推測されます。
外資系の採用戦略として、研修などが充実した日系証券で2~3年経験した若手に、現在の2倍程度の給料を提示してヘッドハンティングするというものが多く、若いうちは外資の方が必然的に高めとなります。
一方で、トレーダーの経験年数が伸びてくると日系⇔外資間の転職がどちらも発生し、それぞれ高額報酬を提示して人材を引き抜き合う形になるため、外資の方がいつも高いとは言い切れなくなります。
トレーダーの収入をより詳しく解説
-

-
証券トレーダーの収入の仕組みと年収レンジ【実体験をもとに紹介】
2025/7/19
「大手の証券トレーダーって、実際どのくらい稼げるの?」 金融業界やトレーダー職に興味を持っている人にとって、年収や報酬体系はやはり気になるポイントではないでしょうか。 結論から先にいうと、だいたい下記 ...
Q. 休みはとれますか?
A. 業務の引継ぎができれば問題なくとれます。
証券トレーダーはチーム単位で働く仕事なので、同僚や部下に不在中の引継ぎを行えば、好きなタイミングで休暇を取得することができます。

筆者は毎年、有給をほぼ100%消化していました。
また、多くの会社では「ブロックリーブ」という、数日間連続で休暇を取ることが義務付けられ、その間は会社関係者に接触することすら禁止、という制度があります。
これによって引継ぎの円滑性を確認し、不在中にアクセスログなどを調べて不正を検出できるということになっています。
【証券トレーダーのキャリアパス・将来性】について
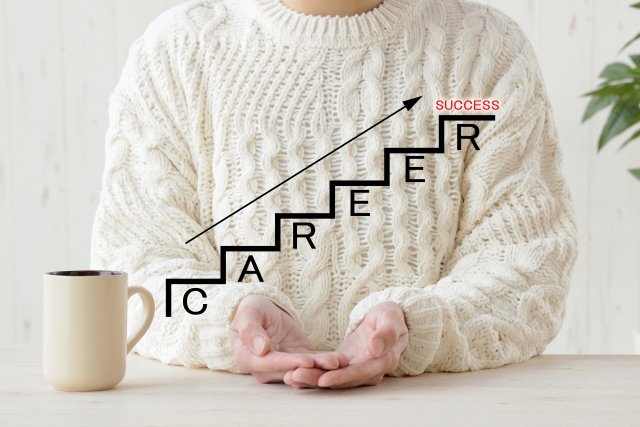
Q. 年齢を重ねるとトレーダーの仕事は難しくなりますか?
A. いろいろな相場を経験している分、年長者が有利だと思います。
あまり反射神経で勝負しているわけではないため、どちらかといえば経験により獲得される勘が有利に働きやすい仕事だと思います。
実際、部長クラスとしてチームをマネジメントするような立場になっても、現場でマーケットに参加している人(プレイング・マネージャー)が多いです。
しかし、やはり会社員なので長く実績を積んできた人物ほど出世しやすく、場中ですらスケジュールがミーティングで埋まるために、マーケットに向き合う時間は減っていく傾向にあります。
Q. トレーダーからの出世ルートやキャリアパスはどのようなものがありますか?
A. 社内で順調に出世すればそのままマネージャーになりますが、同業他社やヘッジファンドに転職してトレーダーを続ける人も多いです。起業家、個人トレーダーという道もあります。
トレーディング部門のポストは限られているため、全員がトレーディングチームのマネージャーになれるわけではありません。
年次が高くなってきたものの、直上のポストに空きがない場合は、セールスやストラクチャリングなど、他部署のボスとして役職を与えられることもあります。
また、トレーダーの転職市場は流動性が高いです。
シンプルに報酬アップや、出世枠の限界感から同業他社に転職したり、ヘッジファンドに転職して、これまで顧客として接してきた運用の世界に入っていく人も少なくありません。
ヘッジファンドとしても、証券トレーダー経験者はマーケットの裏側の仕組みを熟知しているため、一種の修業期間を経た人物として、証券トレーダーをヘッドハンティングするという目線を持っています。
ヘッジファンドマネージャー達のインタビュー集
その他、高収入であることを活かしてトレーダーを辞め、会社を立ち上げてスタートアップビジネスを始めるという人もそこそこいます。
一方で、筆者のように個人トレーダーになるパターンも確かにありますが、この選択肢をとる人物はかなり少数派のようです。
▼ 関連記事
-

-
【FIREの規模別】FIREの種類と必要資金、戦略を徹底解説 目指すならどれ?(王道・初心者向け)
2025/7/8
「いつかは会社に縛られず自由に暮らしたい」 そんな思いを一度は抱いたことがある方も多いのではないでしょうか? 近年注目を集めるFIRE(Financial Independence, Retire E ...
Q. セールスなど他の職種からトレーダーになれますか?全く別業界からの転職は可能ですか?
A. 日系本社や外資系の国内拠点に勤務する社員であれば可能性があります。リテールのセールスや完全に別業界からの転職は難しいです。
上記のように、トレーダーの仕事を近くで見ることができる社員は、希望を出してポストに空きがあれば、トレーダーとして配属されるパターンはそれなりにあります。
一方で、同じ証券会社内であっても、リテール・セールス(個人向け営業)は別世界であり、本社部署を経験せず直接トレーダーになるのは難しいです。
また、業界未経験で転職してトレーダーになったというケースもほとんど聞いたことがありません。
Q. 逆にトレーダーからセールスなど他部署にはいけますか?つぶしが効かないと聞きましたが他業界への転職には不利ですか?
A. トレーダーから他部署に行くことも少ないですがあります。また、トレーダー経験者は他業界でも活躍できる可能性が高いです。
筆者の上司は、
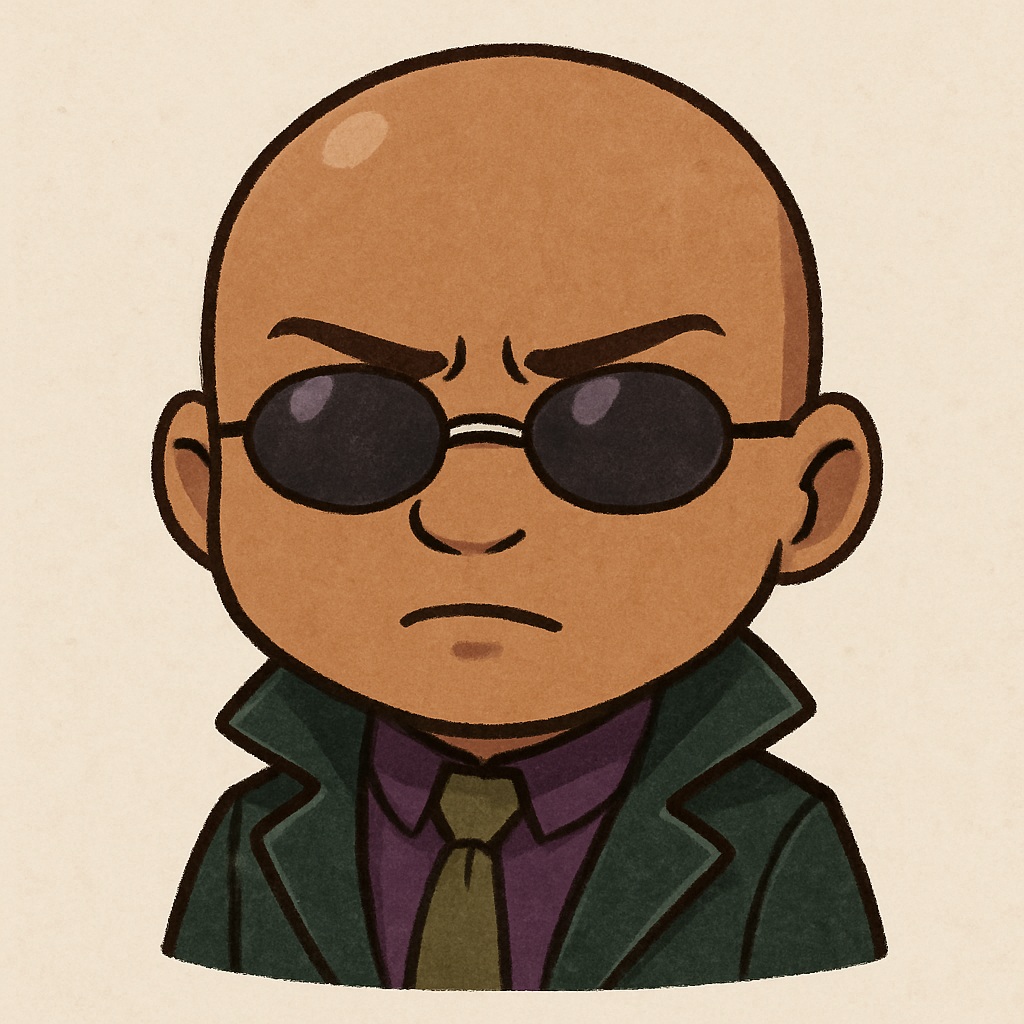
トレーダーは楽しすぎるから、一度経験すると他の職種に行きたくなくなる
と冗談めかして言っていましたが、あながち間違っていないと思います。トレーダーは楽しい仕事です。
また、トレーダーとして採用されるような人は、ビジネスパーソンとして優秀な人材である場合が多く、その持ち前の頭脳を活かして他業界でも活躍する人物になれる可能性が大いにあります。
転職の際に苦労する場面があるとすれば、トレーダーとはどんな仕事なのかあまり知られていないために、前職やスキルの説明が難しいという点です。

このブログを転職先の採用担当者に読んでもらうハモ!!
就活生向け【証券トレーダーへの就職】について

Q. トレーダーに向いている人の特徴は?
A. 地頭が良く、数的感覚に優れ、コミュニケーション力がある人材です。
いわゆる「仕事ができそうな人」、そんな人物がいたら当然引っ張りだこでしょうと思われるかもしれませんが、実際その通りです。
トレーダーの採用基準は非常に厳しい狭き門なのです。
上記3点のバランスがうまくとれた人物すらそうそういませんが、さらにストレス耐性、好奇心(学習意欲)の高い人材が好まれます。
必然的に高学歴の理系大学生・院生が候補として多くなりますが、トレーダーとクオンツ(分析やモデル開発を行う仕事)で迷う場合も多いです。
彼らに対して筆者がよく言っていたのは、

70%~80%の確信度で仕事を進めることに抵抗がないですか?
ということです。
トレーダーは時間制限に追われがちな仕事なので、情報を納得いくまで精査できないことも多々あります。
この点を受け入れられるかどうかは個人の好き好きなので、よく自己分析をするしかありません。
Q. 向き不向きではなく、トレーダーに多い特徴は?
A. 論理的、極度の負けず嫌い、せっかち、ゲーム・ギャンブル好き、などです。
いずれも良くも悪くも、といったところですね。
採用の基準を考えると論理的な人物は向いているでしょう。
また、トレーディングはゲームや勝負事にも共通する部分があるため、そこに魅力を感じた人物が応募してきやすいのかもしれません。
実はポーカーや将棋の全国大会で〇位入賞経験がある、というトレーダーも結構います。
Q. 学歴は必要ですか?学歴フィルターはありますか?
A. 高学歴は事実上必須と言わざるを得ません。
地頭や数的感覚が優れた人物≒高学歴の理系という連想のためか、日本における大手証券トレーダーは東大・京大・東工大、早慶の理系学部出身という人物が非常に多いです。
特に採用に人手をあまりかけることができない外資系では、このような「学歴フィルター」が非常に顕著になります。
上記のようないわゆる「高偏差値大学」出身でない場合でも証券トレーダーになる道は閉ざされてはいませんが、学歴を凌駕するほどの光るポイントが必要です。
例えば「プロ棋士レベルの将棋の実力がある」、「ポーカーの世界大会で上位入賞」、「数学オリンピック優勝」など、誰の目にも明らかにすごいと分かる強みです。
学歴で応募者を入口からフィルタリングするかどうかは会社によって異なります。
しかし、筆者は学歴でフィルターされていない状態の就活生をたくさん見てきた中で、(トレーダー候補という観点で)優秀だと思った学生は、後から確認したにもかかわらず、ほとんど高学歴大学の出身でした。
もちろん、どの大学にも優秀な学生とそうでない学生がいますが、効率的な採用という観点において、筆者は学歴フィルターが結果として非常に有効であるという意見に傾かざるを得ません。
また、逆に立派な学歴があればトレーダーになりやすいというわけでもありません。
選考過程では偏差値の高い大学受験を突破した多くの候補者の中で、どのような光る個性を持っているかが重要になります。
Q. 証券トレーダーになるにはどのようなルートがありますか?
A. 新卒採用でトレーダーを希望するのが基本ルートです。
「Q. セールスなど他の職種からトレーダーになれますか?全く別業界からの転職は可能ですか?」にもあるように、他部署からトレーダーになるパターンはありますが、レアケースです。
他の部署で修行してからトレーダーになりたい、というキャリアパスを描いている学生もいますが、もしご自身にいつかトレーダーをやってみたいという気持ちがあるならば、新卒の時点でトレーダーを希望するのが一番の近道です。
Q. 学生のうちにやっておくと就職で有利なことは?
A. 強いて言えば英会話を磨きましょう。
トレーダーはセールスほど流暢な英会話能力は重視されないため、苦手だからといって致命的な減点にはなりませんが、得意であるに越したことはありません。
他の候補者と差が少ないのであれば、英語が得意な方が選ばれやすいでしょう。
一朝一夕で身につくようなスキルでトレーダーの就活を突破するのは難しいですが、英語は入社後も必須のスキルなので、時間がある学生のうちに鍛えておくことが有効です。
外務員資格や証券アナリスト資格を先んじて勉強する学生もいますが、苦労のわりに就活でのアピール手段としては弱い印象です。
結局は入社後にほぼ全員取得することになるため、「学生のうちにしかできないこと」を充実させたほうがよいと思います。
Q. おすすめの書籍や学習リソースはありますか?
A. 時事対策として日経新聞、周囲と差をつけるなら"ジョン・ハル(著) フィナンシャルエンジニアリング"を読みましょう。
金融用語や話題のテーマが出てきても大丈夫なように、日経新聞を毎日読んでおくのは効果的です。

電子版でもOKハモ!
"ジョン・ハル(著) フィナンシャルエンジニアリング"はトレーダーが入社後に教科書として読むことが想定される書籍です。
これを就活のために読んだとアピールできれば選考過程でも一目置かれます。
分厚い本ですが、非常によくデリバティブの基礎がまとまっており、デリバティブビジネス関係者からは聖書とも言われる名著です。
デリバティブ担当にならなくても、この本で触れられている多くのトピックは前提知識として身に着けているトレーダーが多いです。
デリバティブビジネスのバイブル
Q. 個人で株をトレードしている経験は役に立ちますか?
A. 役に立たないわけではありませんが、限定的です。
個人で株を売買してトレーダーに興味を持ったという学生は多いです。
興味の入り口という点では歓迎されるはずですが、トレードのスキルがそのまま証券トレーダーの仕事に活かせるかどうかは微妙なところです。
プロップファーム(自己勘定で会社の資金を運用する会社)であれば、やっていることは個人トレーダーの延長線上なのでスキルを活かせる場面は多いと思います。
一方で、大手証券トレーダーはマーケットメイク業務として商品のプライシングをするのが仕事です。
仕組債・エクイティスワップ等の個人投資家が取り扱うことができない商品や、先物と個別株で何十億円ものロングショートポジションを多数抱えたりするため、見ているものが個人とは全く異なるのです。
したがって、「個人トレーダーとして稼いだから証券トレーダーになっても活躍できる」という自己アピールは、やや的が外れている可能性があるため注意が必要です。
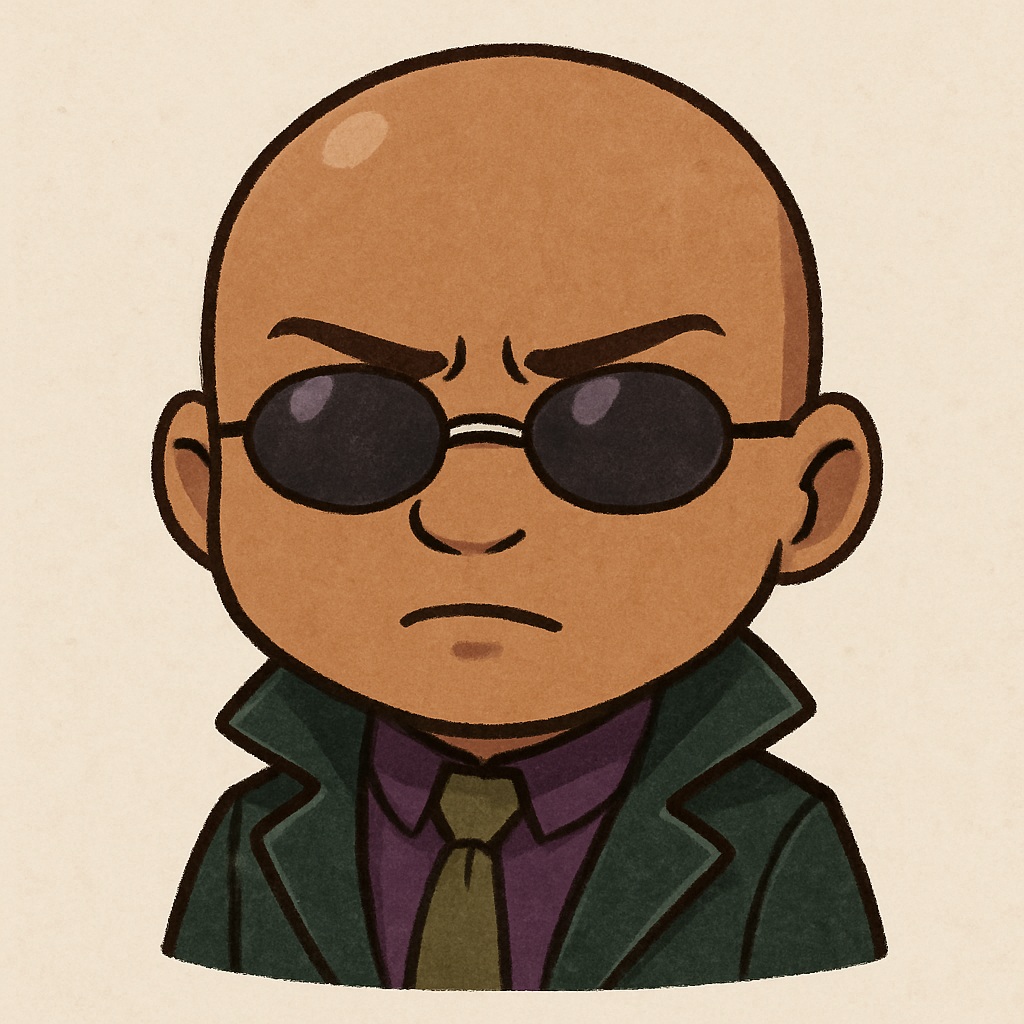
じゃあヘッジファンドやプロップファームに行けば?
と言われてもスムーズに返せるようにしておきましょう。
逆に、個人トレーダーをやるにあたり、証券トレーダーを経験したことは、業界の裏側や仕組みを熟知しているという意味で、非常に有益だと筆者は思います。
プロップファームの書籍
Q. 数学やプログラミングスキルは必須ですか?
A. 数的感覚はかなり重視されます。プログラミングスキルはやや加点対象ですが、必須ではありません。
面談の際、社員から突然計算問題を出される、という場面はとても多いです。
因数分解や素数の仕組みを利用するなど、少しひねって解答を導くようなタイプがよく出題される印象です。
間違えたから落ちるとも限りませんが、単なる暗算能力だけでなく、「意表を突かれても冷静に対処するメンタル」、「論理的に道筋を考える能力」などが同時に評価されています。
突然出されるクイズの例
Q. 2,499は素数ですか?
A. 素数ではありません。
(2,499 = 2,500 - 1 = 50 × 50 -1 = (50 - 1) × (50 + 1) = 49 × 51だから)
プログラミングスキルに関しては、機械学習を研究していた、などかなり高度なレベルであれば評価される可能性は高いです。
しかし、プログラミングと日常的に向き合う仕事ではない(それはクオンツやITの仕事)なので、単にC言語やPythonが書けます、とアピールするだけではトレーダーの選考を通過するにはやや弱いかなと思います。
Q. 英語力はどれくらい必要ですか?
A. 得意であればあるほどよいですが、苦手なトレーダーも多いです。
しかし、実務で英語を使う機会は非常に多い(完全に英語だけで仕事をすることもある)ため、たとえ苦手だったとしても入社後には一定のレベルに追いつくことが要求されます。
誰が聞いてもカタコトの日本語英語をまくしたてるトレーダーなどよく見る光景です。
得意/苦手ではなく、英語を使って仕事をする覚悟があるかどうかのほうが重要です。
Q. 必要な資格や、勉強しておいた方が有利な資格はありますか?
A. 必要な資格はありません。証券外務員や証券アナリストは有効ですが、内定獲得後でも十分でしょう。
特定の資格を取得していることが、トレーダーの採用に大きく有利に働くことはありません。
しかし例えば、高校生で英検一級をとった、などそのまま自分のアピールポイントにつながるような資格があれば、選考をスムーズに乗り切れる可能性はあります。
【証券トレーダーの精神面・人間関係】について

Q. トレーダーは精神的につらい仕事ですか?
A. マーケット自体が持つ厳しさに向き合う必要があるとともに、集団の一員としてのストレスがあります。
相場でお金を稼ぐことは、どのような形であるにせよ簡単ではありません。
トレーダーはまずマーケットが提示する様々な精神的試練を乗り越え続けなければならない仕事です。
そして会社に所属するトレーダーは、お金を稼ぐことを直接的に期待される存在です。
肩書が上がるほど年収はうなぎ登りですが、同時に収益に対するプレッシャーも跳ね上がってきます。
課長や部長としてチームを率いるようになると、自分だけでなく部下の成績に対する責任も負うことになってきます。
自由に魅力を感じるか、大きなプレッシャーを負担に思うかは人それぞれです。
トレーダーは向き不向きがはっきりしているため、誰にでもおすすめできるわけではありませんが、精神面と金銭面の両方で相応の報酬が得られる世界だとも思います。
Q. プレッシャーにどう対処していますか?
A. 人それぞれですが、長期的な目線で考えることとチームプレイが大事です。
特にトレーダーは短期の結果に一喜一憂してしまいがちですが、成果は年度毎に評価されるため、長い目線で走りぬくというマインドが大切です。
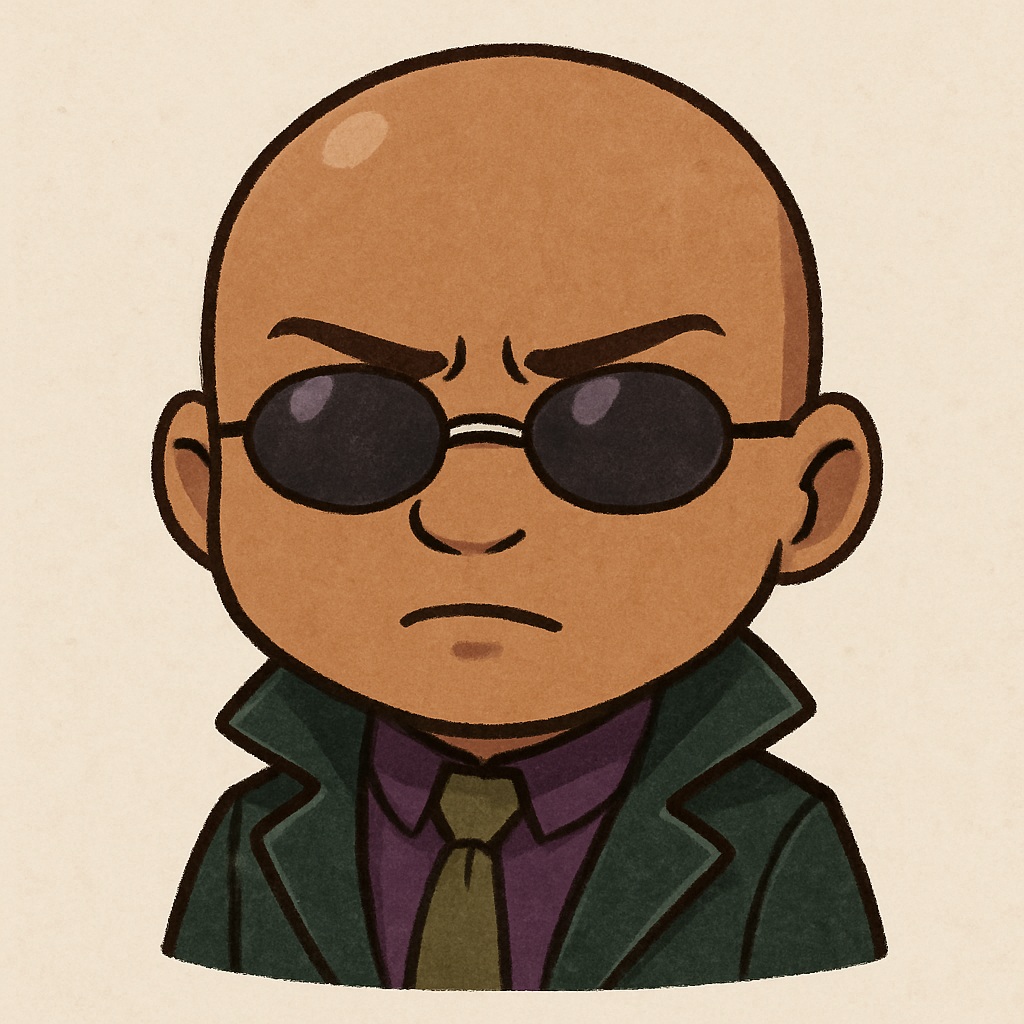
トレードは短距離走ではなくマラソン
と筆者の上司もよく言っていました。
また、組織上の対策として、一人で問題を抱え込まずに相談するという意識が必要です。
外資系では人数が少ないため、チームと呼べるほど人がいない場合も多いですが、直属の上司は部下の成績が自分の評価に直接結びつくため、パフォーマンスを上げるための相談には乗ってくれるはずです。
Q. 社内の雰囲気はピリピリしていますか?
A. 証券会社のマーケット部門は独特のエネルギッシュな雰囲気に満ちています。
ピリピリ、ギスギスという表現は少し違うと思います。
筆者が初めてトレーディングフロアを訪れたとき、その独特の雰囲気に、

ここは戦場だ…。
と思いました。
なんとも口で説明しがたいのですが、トレーディングフロアの雰囲気に関しては、"マイケル・ルイス(著)ライアーズ・ポーカー"という書籍に描かれているフロアの様子に近いものが今でもあります。
トレーディングフロアに迷い込んだ部外者に対し、著者のマイケル・ルイス氏が抱いてしまった"ある感情"はとても共感できます。
金融に詳しくない方でも面白く読める本なのでとてもおすすめです。この本を読んで証券トレーダーを志したという人もたくさんいます。
ウォール街のハチャメチャな真実の物語
Q. 「稼いでいるトレーダー」に共通するメンタルとは?
A. 長期的な目線を持っている、建設的で論理的な思考をしている、状況に応じて柔軟に考えを変えることができる、などです。
これは一般的な個人トレーダーなどにも共通する事項かもしれませんが、証券トレーダーは「会社としてビジネスを行う」というより広い文脈でこれらの思考を活用しています。
一人で完結する仕事ではないため、どうすれば他部署や他のトレーダーと一緒に大きな成果を上げられるか、という視点を持つ必要があるのです。
したがって、上記のようなメンタルはトレーダーのみならず、仕事ができるビジネスパーソン一般に共通する特徴ともいえます。
【その他の質問、金融業界、株式市場全般】について

Q. 実はインサイダー取引をやっているのではないですか?証券トレーダーは「インサイダー」ではないのですか?
A. 証券トレーダーは「インサイダー」に該当せず、もしインサイダー取引を行った場合は法令に基づいて厳正な処罰が下されます。
非常に多い、そして迷惑な誤解なのですが、証券トレーダーは法律で定義される「インサイダー」ではありませんし、インサイダー情報を入手してしまった場合は職務の遂行に重大な影響を及ぼすため、絶対に入手できないように会社規模での対策がとられています。
証券会社においてインサイダー情報を持っている可能性がある(いわゆる「イン部署」)は、投資銀行部門(IB部門)、リサーチ(企業情報調査部門)などがあります。
これらの部署とトレーダーは別フロアなどで物理的に隔離され、社内のコミュニケーションでも情報管理が徹底されています。
インサイダー取引をはじめとする金融犯罪は、発覚すれば業界追放レベルの重大な違反であり、このような法令違反を行うことによるリスクは、そのリターンを遥かに上回っています。
正常な倫理観を持つトレーダーは「インサイダー情報なんて絶対欲しくない」と思っているはずです。
ごくまれに「●●社のトレーダーがインサイダー疑惑」というニュースを見ますが、倫理観の欠如もさることながら、リスクとリターンを比較する能力が欠如しており、そもそもトレーダーに向いていないと言わざるを得ません。
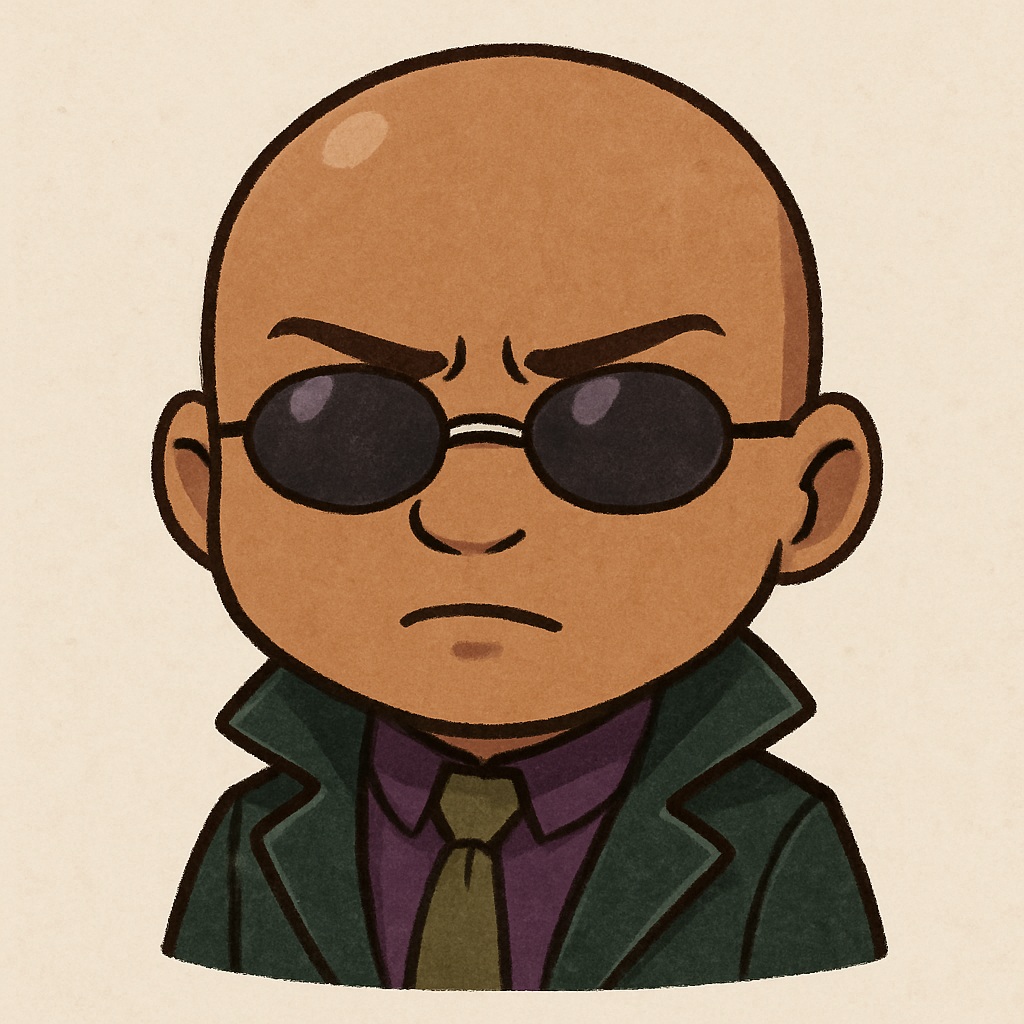
インサイダー取引やってますか?
と尋ねることは、
あなたは犯罪者ですか?
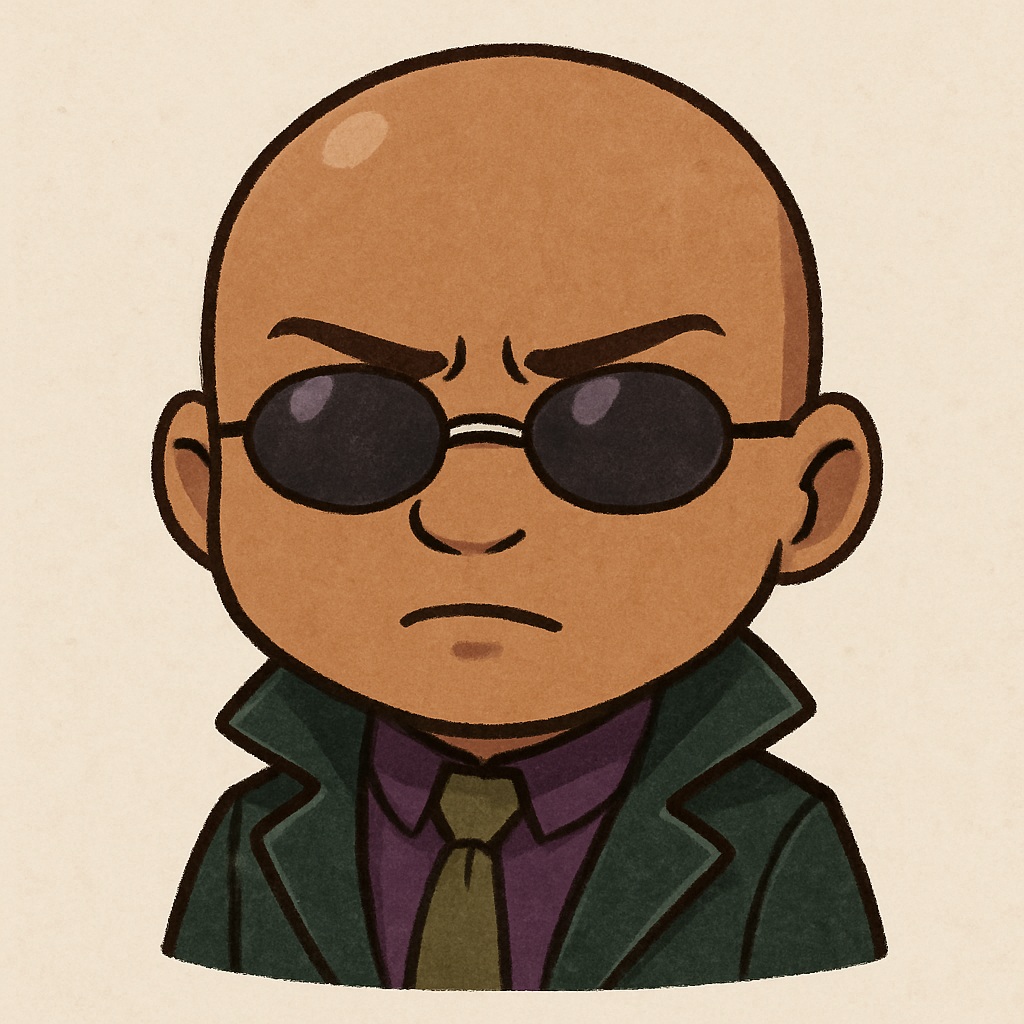
と聞いていることと同じなので、大変失礼な質問です。口に出すのはやめましょう。
このあたりの事情に関しては、"大森 泰人(著)「霞ヶ関から眺める証券市場の風景 -再び、金融システムを考える」"という書籍にて、金融庁として不公正取引を取り締まる立場から歯に衣着せぬ口調で語られています。
インサイダー取引とは
インサイダー取引
インサイダー取引とは、上場会社の関係者等が、その職務や地位により知り得た、投資者の投資判断に重大な影響を与える未公表の会社情報を利用して、自社株等を売買することで、自己の利益を図ろうとするものです。そうした情報を知らされていない一般の投資者は、不利な立場で取引を行うこととなり、証券市場の信頼性が損なわれかねないため、金融商品取引法で禁止されており、違反者には証券取引等監視委員会による刑事告発や課徴金納付命令の勧告が行われます。
Q. フロントランニングのようなズルはしていないのですか?
A. フロントランニングを疑われないように細心の注意を払っています。
上記インサイダー取引に関する質問のように、基本的に法令違反を行うことによるリスクはそのリターンを遥かに上回っているため、トレーダーはなるべく疑われることすら避けようと努力するのが自然です。
証券トレーダーがフロントランニングを行いかけてしまうケースは大きく分けて2つあり、
①セールス・トレーダーの委託注文を知ってしまう
②他のトレーダーがプライシングしている最中の商品を売買してしまう
というパターンがあります。
①は情報管理の問題なので、セールス・トレーダーは執行が終わっていない委託注文に関する情報を漏らさないように細心の注意を払っています。
②に関して、そもそもプライスを聞かれた時点ではまだ顧客がトレードをするかどうか確定していないため、明らかにフロントランニングかと問われれば微妙です。
しかし、少なくとも同じ商品をトレードする可能性があるトレーダー同士では、今何をプライシングしているのか、互いにコミュニケーションを取り合うことで疑われないように注意しています。
フロントランニングとは
フロントランニング(ふろんとらんにんぐ)
金融商品取引業者またはその役職員が、顧客から有価証券の売買の委託等を受けた場合、その売買を成立させる前に、自己の計算において同一銘柄の売買を成立させることを目的として、顧客の注文より有利な価格(同一価格を含む)で有価証券の売買を行うことをいい、金融商品取引法で禁止されています。
平たくいえば、お客さんから注文が来たら先回りして自分の注文を約定させるというズルです。
Q. 大損した経験はありますか?
A. 2020年のショック時、対顧客で下げに弱いポジションを大きく抱えていたために巨大な損失を出したことがあります。
当時の筆者はまだ若手という扱いで、上司の管理下で対顧客ビジネスを回していたため、私に対して直接的な損失に関する追求はありませんでした。
一方で、管理者である上司はかなり厳しい追及を受けたようでした…。
対顧客のビジネスなので、期待値的に大きなプラスが見込まれるトレードを実行し、結果的に最悪のシナリオが最悪のタイミングで起きた、というのが事実です。
最悪が想定できていなかったのではなく、そのリスクを呑んだ上で(上司とも相談の上)実行することに決めたトレードでした。
トータルでみれば損失額はそこまで大きくないものの、「大きな含み益が急に損失に転じた」という点が、会社の上層部にとって非常に見栄えの悪い形でした。
含み益が含み損に変わるのは誰にとっても苦痛なものですから当然です。
Q. 逆に大儲けした経験はありますか?
A. 近年のショック相場の多くで大きな利益を上げることができました。
オプショントレーダーである筆者は、マーケットのボラティリティが急激に高まるタイミングで儲かるトレードが非常に得意です。
その代わり、ボラティリティが低迷する相場では非常に苦戦を強いられます。
筆者は2016年入社だったので、幸運なことに原油大暴落、Brexit、第一期トランプ大統領選挙など、「ブラックスワン」と呼ばれるショック相場イベントが盛りだくさんで、オプショントレーダーとして学ぶ機会が多い相場を何度も経験できました。
ブラックスワン三部作
2017年ごろから、特にオプション戦略について自分なりの取り組み方が固まり始め、2018年のVIXショックで最高益を出すことができ、自分のやり方に自信が持てるようになりました。
勝てるようになった転換期はいつか?と聞かれれば、この時期ということになると思います。
この頃から、将来は個人トレーダーとして生計を立てることができたらいいなとぼんやり考えるようになりました。
また、上の質問において2020年に大損したと書いていますが、対顧客ではないトレードにおいては、やはり暴落相場ということもあって、私のオプション戦略はかなりうまくいきました。
Q. 証券会社のトレーダーは株式市場全体が上がったら儲かり、下がったら損しているのですか?
A. 結果としてそのようなケースは多いですが、重要なのは市場の盛り上がりです。
まず、証券トレーダーは株などを「買って持っておく」仕事ではありません。
商品の値付け、ポジション管理を行う中で、必要があればショートポジション(空売り、マーケットが下がったら儲かるポジション)をとることも頻繁にあります。
したがって、証券会社がいつも株をロング(買い持ち、上がったら儲かる)しているというのは大きな誤解です。
証券トレーダーの収益の源泉はマーケットメイクにおけるスプレッドです。
収益を実体化するには、顧客に売買してもらわなければなりません。
マーケットが荒れている環境では、市場の売買代金(出来高)が増え、証券会社に入ってくる注文も自然に増加するため、収益環境は良好ということになります。
イケイケの上げ相場はもちろんですが、暴落シーンでも同様に注文が活発化するため、証券会社にとっては悪くないといえます。
一方で、マーケットが落ち着いており、「閑散」と言われてしまう相場で稼ぐのは非常に厳しくなります。
Q. 顧客と反対ポジションをとるならば、顧客の損がトレーダーの儲けになるということですか?
A. トレードが成立した瞬間はそうですが、実際はヘッジ取引を行うため、顧客の損益とトレーダーの損益は切り離されています。
証券トレーダーの仕事は、自分が提示したプライスで顧客の反対ポジションをとることです。
ただし、顧客がとりたいポジションとまさに反対のポジションをとりたい、という瞬間は非常に稀です。
したがって、トレード後に何らかのヘッジ取引を行って、ポジションが逆行しても損をしないような形に整えるのが基本です。
ヘッジ取引の例
Q. 経済の見通しは?上がる株を教えてください
A. 全く分かりません。隠しているのではなく、本当に分かりません。
トレーダーあるあるの質問です。トレーダーを名乗ると誰もがこの質問を受けることになります。

またきたハモ。
よく誤解されるのが、トレーダーは未来を予想してお金を稼ぐ仕事でしょ?というものです。
未来が予想できる ⇒ お金が稼げる
これは正しいです。未来の株価を知っていたならばどんなに楽なことでしょう。
しかし、未来を正しく予想できることはほとんどありません。逆にこちらはどうでしょうか。
お金が稼げる ⇒ 未来が予想できる
これは間違いです。未来が予想できなくてもお金を稼ぐことは可能です。
トレーダーが実際にやっているのは、未来において実現したらお金が儲かる可能性の高い(正確には"期待値"の高い)シナリオにベットし、外れたらごめんなさい、と損切りをするのをひたすら繰り返すことです。
したがって、「今の時点で」どんな行動がベストなのかを考え実行しているため、重要なのは予想が当たったかどうかではなく、期待値の高い行動を毎回とり続けることができているか、ということになります。
マクロマーケット分析が得意なトレーダーであれば、経済の見通しについて独自の相場観を述べてくれることでしょう。
しかし、どんなに優れたトレーダーでも予想が当たる確率は外れる確率とほぼ同じです。
勝ち組と負け組の差は、予想を高確率で当てる能力ではないと言い切ってしまってよいと思います。
Q. 証券トレーダーから個人トレーダーになってよかったことは何ですか?
A. 業界構造を知れた他、証券会社には特別な秘密や後ろめたい戦略などないと分かったことが大きいです。
詳しくはプロフィールに記載しましたが、筆者は在宅勤務が認められない、会社とのズレ、体調不良がきっかけで退職し、個人トレーダーになることを決意しました。
▼ 筆者の詳しいプロフィール
-

-
運営者プロフィール:就職、不動産FIRE、個人トレーダー、当ブログについて
2025/7/19
基本情報 簡単なプロフィール 名前:Mewcle(みゅーくる) 30代、個人投資家/資産管理法人オーナーとして、不動産と株トレードで生計を立てています。 大手証券会社で株トレーダーとして働きながら20 ...
証券トレーダーを経験してから個人トレーダーになったことは、次のような多くのメリットがありました。
証券トレーダーを経験してよかったこと
✅毎日半強制的にマーケットを監視することで、実戦的な感覚が養われた
✅プロ向けのリスク管理ツールでポジションをコントロールするスキルが身についた
✅マーケットメイクの仕組みや大口顧客の注文方法など、マーケットの裏側への深い理解
✅ブルームバーグ端末や自社トレーディングツールなど個人では触ることが難しい高品質なシステムを使用できた
✅給与水準が非常に高いため、FIREするための資金を貯めやすかった(生々しいですが本当です)
この中で一番重要だと思うのは、「マーケットの裏側への深い理解」です。

証券会社が売り仕掛けをしているハモ!
個人投資家をだまそうとしている!
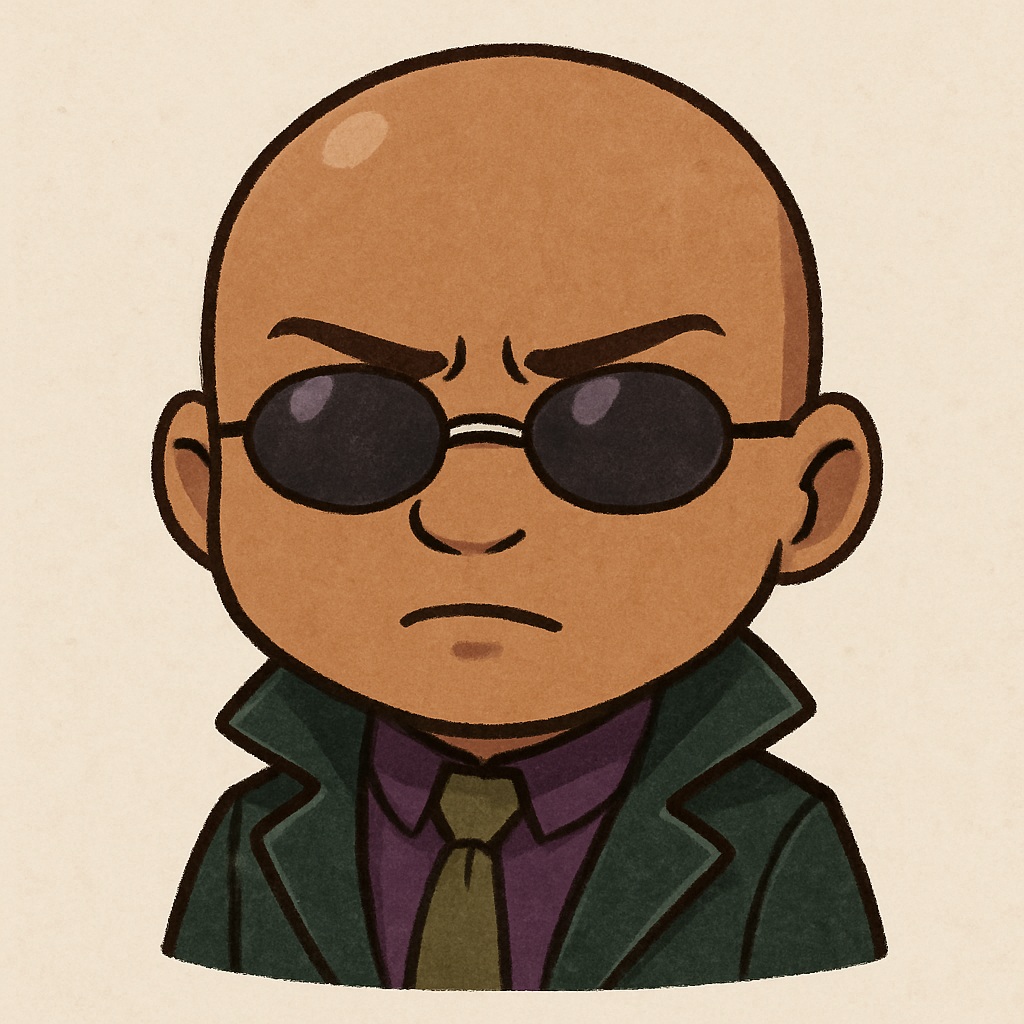
などコメントする方をたまに見かけますし、筆者も証券トレーダーを経験していなければ、「そうかもしれない…」と思ってしまったかもしれません。
実際は誰か(特に個人投資家)を食い物にしようとしてオーダーを出すようなことはありませんし、できなくはないとしても、時間と労力の無駄であることがほとんどです。
"証券会社には特別な秘密や後ろめたい戦略などない"
ということを知ることができたのはとても大きな学びだったと思います。
個人トレーダーとして、自己責任を心の底から受け入れる助けとなったのです。
(もちろん顧客情報は絶対に漏洩できないので秘密です。また、インサイダー取引で業務改善命令を出される会社もあったりしますが、さすがにそういった市場に対する冒涜行為を擁護することはできません。)
まとめ
証券トレーダーは
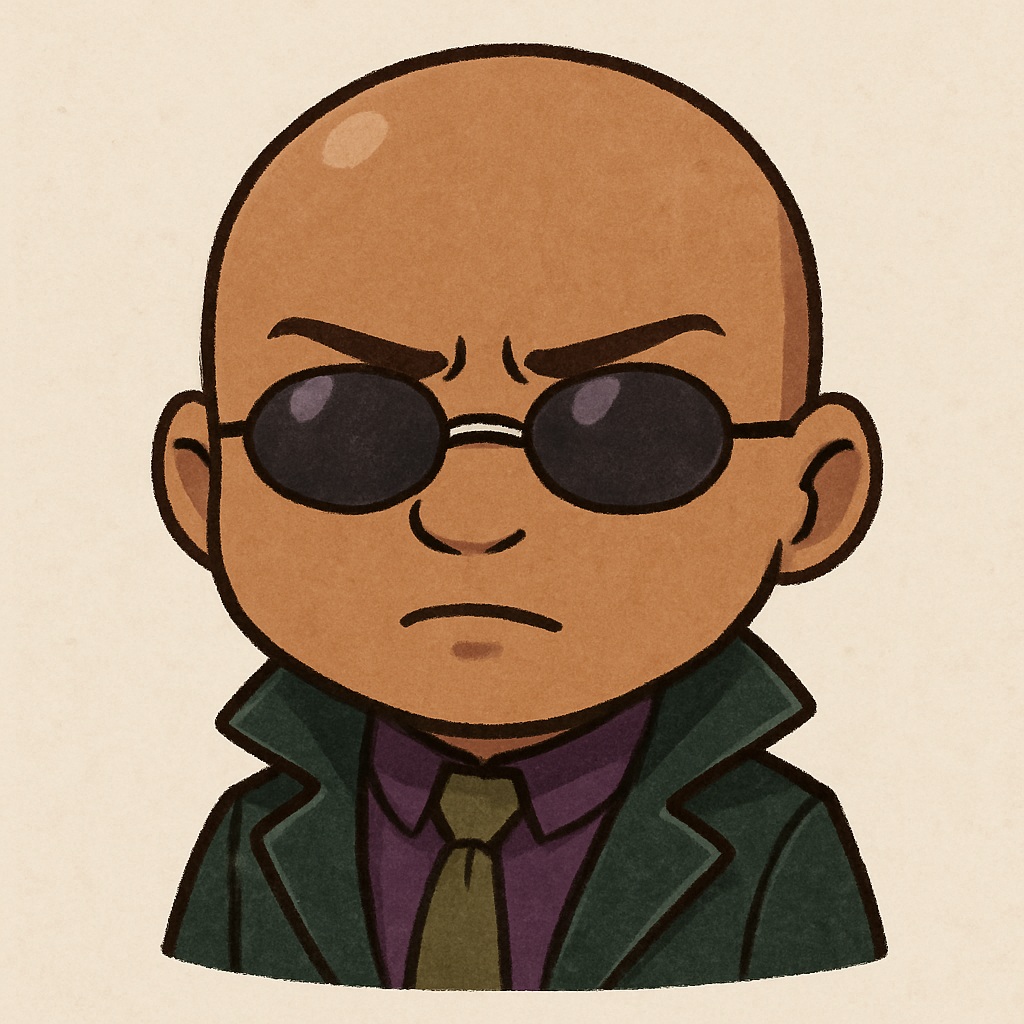
きつそう
精神的に辛そうハモ

と思われがちですが、仕事内容と報酬の両面でやりがいのある仕事です。
億越え個人トレーダーやヘッジファンドのスーパートレーダーになるには人並外れた才能が必要ですが、証券トレーダーとして成功するには才能よりも努力、根気、コミュニケーションといった泥臭い側面の方が重要です。
この記事で紹介した内容を踏まえ、興味が湧いた方はぜひ証券トレーダーという選択肢を検討してみてください!
当ブログでは新社会人の資産形成を応援する記事をいくつか書いています。単なる一般論ではない視点から投資のコツを紹介しているので、ぜひご覧ください。
▼ 就活生・新社会人向けの記事
種銭を貯めて投資しよう
-

-
投資用種銭の貯め方【節約・ポイントサイト・副業・運用まで】
2025/7/3
「株や不動産で人生を変えたい。でも…“資金がない”という現実に何度もため息をついたことはありませんか?」 実は、これまで多くの人が同じ壁にぶつかっています。 小さな資金を雪だるま式に大きくするには、ま ...
-

-
ハピタスで10万円稼ぐ5つの方法 初心者向けポイ活ガイド
2025/7/3
「副業を始めたいけど、時間もスキルもない…」 「できればお金をかけずに、スキマ時間で少しでもお小遣いが増えたら…」 そんな方におすすめなのが「ポイ活」、特に評判の高い『ハピタス』です。 筆者も実際にハ ...
-

-
【初心者向け】ハピタス×FXで高額ポイントをもらう方法をわかりやすく解説!
2025/7/3
「ハピタスのFX案件ってお得そうだけど、ちょっと怖い…」「FXって難しそうだし、損したらどうしよう…」 そんな不安をお持ちの方へ! この記事では、FX初心者でも安心してハピタスでポイントを獲得できる方 ...
資産形成の指針をたてる
-

-
【目的から逆算】新社会人の資産形成ガイド
2025/7/8
将来のお金の不安、ありませんか? 「なんとなく貯金しなきゃ」「投資が必要らしい」と思っていても、いざ何をすればいいか分からない…。 それは、"目的"が定まっていないからかもしれません。 資産形成の第一 ...
-

-
【新社会人向け】資産形成今すぐやるべきことリスト 20代で差がつくお金の習慣
2025/7/8
社会人になったばかりで、資産形成なんてまだ早いと思っていませんか? 実は新社会人こそ、資産形成を始める最大のチャンスです。 時間という武器を最大限に使える今こそ、お金との付き合い方を見直し、将来の安心 ...
新NISAの使い方
-

-
【初心者向け】新NISAのつみたて枠はオルカン一択でOK 迷わない投信選びのコツ
2025/7/3
「NISAで積立投資を始めたいけど、結局どの投資信託を選べばいいのかわからない…」 新NISAをきっかけに投資デビューした人の多くがぶつかる壁です。 筆者自身も色々な投資信託を調べて購入してきましたが ...
-

-
新NISA成長投資枠の賢い使い方 具体的な買い方と銘柄選びのポイント
2025/7/3
「積立枠はわかるけど、成長投資枠ってどう使えばいいの?」 新NISAが始まり、自由度の高い成長投資枠に戸惑っている方も多いのではないでしょうか。 証券会社のNISA特設ページでも、成長投資枠の使い方が ...
iDeCoを活用しよう
-

-
iDeCoと企業型DCはオルカンでいい?アセットアロケーションの基本と投資信託の選び方
2025/7/8
確かにiDeCoや企業型DCはNISAのつみたて枠とよく似ています。 しかし実は、NISAとiDeCo/DCでは目的も仕組みもけっこう違うんです。それを理解せずに同じように運用すると、思わぬ落とし穴も ...
住宅ローン住み替え戦略
-

-
家を買うだけじゃもったいない!住宅ローンで賢く資産を作る方法
2025/7/3
「自宅は一生に一度の買い物」 多くの人がそう思っていますが、大きなチャンスを逃しているかもしれません。 実は、住宅ローンは「資産形成の強力な味方」になるのです。 この記事では「自宅は負債ではなく資産に ...
FIREを目指す!
-

-
【FIREの規模別】FIREの種類と必要資金、戦略を徹底解説 目指すならどれ?(王道・初心者向け)
2025/7/8
「いつかは会社に縛られず自由に暮らしたい」 そんな思いを一度は抱いたことがある方も多いのではないでしょうか? 近年注目を集めるFIRE(Financial Independence, Retire E ...
▼ この記事で紹介した商品まとめ
高速取引の黎明期をのぞき見る
プロップファームのディーラーが分かる書籍
アメリカのプロップファーム
ヘッジファンドマネージャー達のインタビュー集
デリバティブビジネスのバイブル
オプション入門のおすすめ書籍












